四国八十八ヶ所
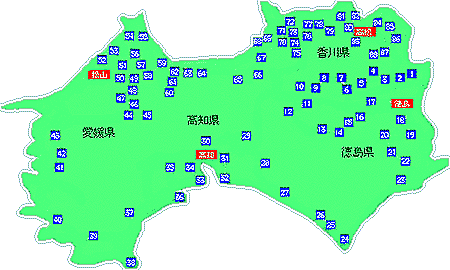
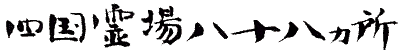
基 礎 知 識
| 八十八ヶ所巡りの由来 |
| 弘法大師が42歳の時、四国八十八ヶ所の霊場を開いたとされる。また、弘法大師入定後、高弟真済がその遺跡を遍歴し始まったとされる説がある。八十八という 数は、煩悩の数や、「米」の字を分解したもの、または男42、女33、子供13の厄年を合わせた数などという説がある。 札所を巡礼することを打つという。これは、昔の巡礼者が、自分の名前を書いた木札をお寺に「打ちつけていた」ことから使われていた言葉(今では納札にか わっている)。一番札所より始め、八十八番札所まで番号順に巡るのを順打ちといい、逆に八十八番から一番へ、反対に巡礼するのを逆打ちという。「逆打ち」 一回は「順打ち」三回相当のご利益、功徳があるといわれている。「逆打ち」のはじまりは、伊予国の御門三郎が弘法大師に会いたい一心で、霊場が逆から廻っ たのが始まりとされている。 すべての霊場を一遍に打ち上げるのを通し打ち、適当に区間を区切って打つのを区切り打ちという。一番札所からはじめる必要はなく、また一度に全ての寺をまわることもない。一国参りといって、一つの県を一国とし、まわることもある。 |
| 十善戒 |
| 一、不殺生・・・殺生することなかれ 二、不偸盗・・・盗むなかれ 三、不邪淫・・・邪淫することなかれ 四、不妄語・・・偽りをいうことなかれ 五、不綺語・・・虚飾の言葉をいうことなかれ 六、不悪口・・・悪口をいうことなかれ 七、不両舌・・・二枚舌をつかうことなかれ 八、不慳貧・・・貧ることなかれ 九、不瞋恚・・・怒ることなかれ 十、不邪見・・・よこしまな考えを起こすなかれ |
巡礼プラン
四国八十八か所巡礼プランはコチラ

